【3000文字チャレンジ】なぜあの時ぼくは泣けなかったのか。
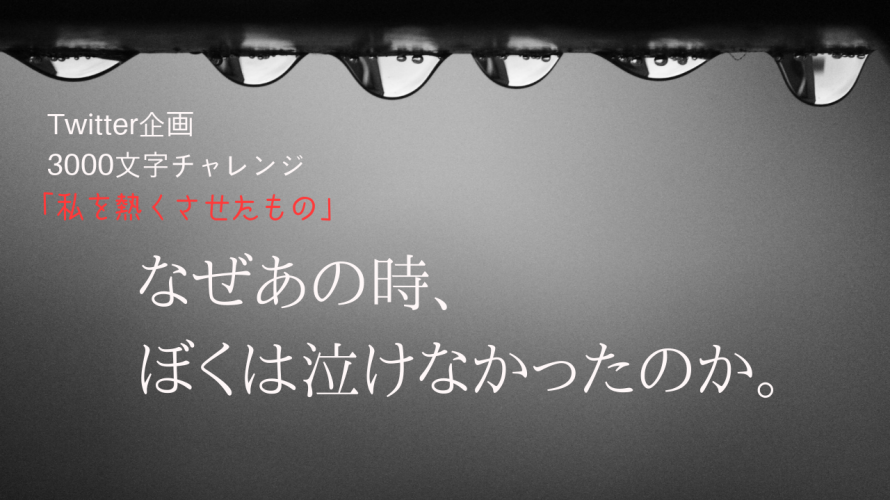
3000文字チャレンジ!お題「私を熱くさせたもの」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回(3/14スタート)の3000文字チャレンジのお題は「私を熱くさせたもの」。
今まで熱くなったことはさまざまあれど、どんなテーマで書こうかなぁと悩みながら、他の方の記事を読んでたんですね。
バイトに熱くなった話、大好きな車や音楽の話、活字大好きで今3000文字チャレンジが熱いというお話、他にも温泉、ヒートテック、松岡修造(笑)などなど。
どの記事も書いた方の歩んできた人生の一端を垣間見れるような内容で、楽しく読ませていただいていました。
その中で、いつも楽しい記事を書いておられるもたろうさん(@mota119)の「実は・・・」という記事を読んだんですね。
その記事の内容をかいつまむと、殺意を抱くほどに仲の良くなかった父親が亡くなり、泣くことはないと思いながらも病室で対面した際に号泣した(短くまとめ過ぎですいません!!)というお話なんですが、なんだかすごく心をえぐられる思いがしたんですね。
いつもなら記事を読んだら、すぐにtwitter上でコメントを残すんですが、、、その時はいいねを押すだけしか出来ず。。。
というのも、ぼくも父を若くで亡くしてるんですが、ぼくは泣くことができなかったんですよね。
父を亡くしたのはもう20年近く前のことですが、ずーっと心の奥底の暗い部分に、父の死に際に泣くことができなかったという思いが、黒い澱のように溜まってるんです。
これは友人にも誰にも話したことのないぼくの自分語り。
この心の奥底に沈んだままの自分の闇と対峙して、中学生の頃の自分と今一度向き合って、何が出てくるか。
思いのままにパソコンのキーボードを叩いてみたいと思います。
ぼくが生まれたのは田舎町で、親は夫婦共働きで忙しく豆腐屋を営んでいました。
祖父の代から始めた豆腐屋で、父は2代目ということになります。
ぼくを宿した母は、もうだいぶお腹も大きくなっていたのに自営業故休むことも出来ず、毎日朝早くから起きて仕事をしていたそうです。
まだ出産予定日の1か月以上前。
仕事中にいきなり陣痛と破水が起こったそうです。
家から産婦人科の病院までが近かったことも幸いして無事出産。
2500g以下の少し小さい身体で生まれてきた赤ちゃんは、年の離れた3人の兄姉にも愛されてすくすくと大きく育ちました。
わが家は親族揃って新興宗教を信仰していて、その教えからあまり病院や薬に頼らない家庭でもありました。
そんな信仰にぼくは反発して、家族内で宗教戦争が勃発しそうになったこともありました。
まぁ信仰に反発してというよりは、休みの少ない自営業なのに、貴重な休みの日は宗教の施設に行ってはお祈りに時間を割く両親を、子ども心にツマらないと感じていたのだと思います。
両親ともに熱心な信仰者で、毎日家の神棚にお祈りを捧げ、ご先祖様に御膳を用意し、他人の幸せを願い、子どもたちにも神の御教えを説くような人たちでした。
母は朗らかで、優しく、いつも明るい人。
何か良いことがあったり、頂き物があったりすると「もったいないことで~」という口癖を発する、常に感謝の心を持っているような良心的な人物です。
父は寡黙で、あまり感情を出さない人、、、だったと思います。
あまり遊んでもらった記憶もないんですよね。
ぼくは上の兄姉からは8年も離れて生まれた末っ子なんで、結構甘やかされて育ったらしいんですが(姉談)
よくある親子のキャッチボールだとか、そういった遊びは皆無だったような気がします。。
ほんとはあったのかもしれませんが、ぼくの記憶からはきれいに抹消されてしまっているようです。
父は仕事以外の家のことは何もしてなかった気がします。
これだけはなぜかよく覚えている出来事なんですが、母がいない時に来客があって、父が客にお茶を出そうとしているんだけど、茶葉のある場所が分からなくて困っているというシーン。
なんでこんなシーンだけを鮮明に覚えているかは謎ですが、その時の「お父さん、かっこ悪いなぁ。」という印象が強く脳裏に焼き付いています。
この強烈に脳裏に焼き付いているシーンのおかげか、ぼくは台所仕事がけっこう好きだったりします。
料理だったり、美味しいお茶を淹れたり、皿洗い、キッチン周りの掃除なんかも。
父親ができなかったことを自分ができているということに、自己満足感を得ているのかもしれません。
そんな両親ともに歌が好きで、毎日、豆腐を作る工場の機械音に紛れながら、演歌を口ずさんで仕事をしていた風景を思い出します。
そんな歌好きのDNAはしっかりと受け継がれていて、ぼくも歌が大好きです。
小学生の頃は、あまり難しいことも考えず、このまま大きくなって豆腐屋を継ぐのかなぁとぼんやりと考えていました。
12歳離れた長兄は、ぼくが物心ついた頃には家を出ていましたし、姉二人もそれぞれの道に進もうとしていましたから、家に残るのはぼくだけなのかなぁと幼心に思ったりもしていました。
よくある学校の「将来の夢は?」みたいなのに「3代目お豆腐屋さん」とか書いてた気がします。
小さい頃は親が喜んだり、お小遣いを貰えるのが嬉しくて、夏休みや冬休みなんかは進んで仕事の手伝いをしていました。
そんな良い子にも、思春期が訪れます。中学生2年生頃かな。反抗期の到来。
まぁ、世間一般的な反抗具合だったと思います。そんなにグレたりとかはなかったですね。
ちょっと親と話したりするのを避けているくらいの感じです。
そんな時期にね、父が倒れました。まだ50代半ばでした。
普段から病院には行かない家庭です。
我慢の限界を超えて、どうにも身体がいうことを聞かなくなってから病院に行って。。
下された診断結果は
末期の胃癌。余命は半年。
こんな状態でも家族は神様がどうだのこうだの言って、宗教の施設に通い詰めになって。。
そんな家族に辟易したのと、病院の白いベッドの上で死を待ち続ける父の姿を見るのが怖くて、結局1回しかお見舞いに行かなかったんです。
その1回すら超短時間で、特に何も話せず。。
あの頃のぼくは弱かった。。バカだった。。そうとしか言えません。
慌てふためいて、それこそ藁にもすがる思いで神頼みの家族を罵り、弱る父の姿を直視できなかった、心の弱いただのバカな子どもだったんです。
さらさらと砂時計の砂が落ちるように時は過ぎて。
忘れもしない2/14。日付を跨いでから数時間しか経ってない夜中のこと。
電話の音に飛び起きて、受話器を耳にあてると聞こえてきたのは母の震える悲痛な声でした。
母のあんな声を聞いたのはあの時の一度きりです。
癌の宣告からちょうど半年で父は亡くなりました。
余命宣告ってこんなにも的中するんだなぁ、と変なところに感心したのを覚えています。
いつも寡黙で真面目で不器用で、何を考えているのか分からなかった父の死。
きっとあの時のぼくは悲しかったはずなのに、涙は流れなかったです。
母や姉の泣き崩れる姿を見ると泣けなかった。ぼくには泣く資格がなかったんです。
いつだって行けたのにお見舞いにすら行かず、献身的に祈りを捧げる家族をバカにしたぼくには、泣く資格なんてないと心のどこかで考えたんだと思います。
父が亡くなって、母は女手一つでぼくを育ててくれました。
豆腐屋なんて出来るわけもなく、毎日大豆の香りと油揚げの油煙が漂っていた店はキレイに解体され車庫になりました。
多くの機械が稼動して、絶え間なく響いていた音もなくなりました。
毎日聞こえてきた歌も聞こえなくなりました。
騒がしかった朝は、父がいなくなったあの日から怖いほど静かになりました。
自分の小遣いぐらいは自分で稼ごうと高校3年間はバイトに明け暮れました。
家にお金もないだろうし、進路は就職かな~と考えているとき、母はぼくに「大学に行きなさい。」と言いました。
ぼくを大学に進学させること。
それが父の遺言だともその時に聞かされました。
奨学金も借りながら大学に行ったぼくは、そこでたくさんのことを学び、多くの友人や、生涯を共にする愛しい人と巡り逢い、今では二人のかわいい子どもにも恵まれました。
父の遺言がなければ、地元で就職し、全く別の人生を送っていたのだと思います。
そして現在。
子を持つ親になって思うこと。
それは、もし自分が家族を残してこの世を去ることになった時、どんな思いを抱くのかということ。
正直、想像するだけでツライです。
自分がいなくなってしまうという恐怖もそうですが、それ以上に、残してしまう家族のことを心配する気持ちの方が強いです。
あの時、ぼくの父は白いベッドの上で、見舞いにも来ない息子に対してどんな想いを抱いたのでしょうか。
今になって、泣いて、泣いて、泣きじゃくって謝りたい。そして伝えたい。
「お父さん、ごめんなさい。そして、ありがとう。」
ーーーーーーーー
-
前の記事
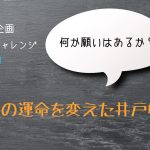
【3000文字チャレンジ】あの人の運命を変えた井戸端会議 2019.03.01
-
次の記事

【3000文字チャレンジ】蒼い朝と翠のさくら 2019.03.17







コメントを書く