【3000文字チャレンジ】「私、饂飩じゃないから。」
- 2020.05.23
- 雑記
- 3000文字チャレンジ, うどん, 創作, 饂飩

3000文字チャレンジ! お題「うどん」
ーーーーーーーーーーーーーー
五月の連休も明け、初夏の風が薫る季節。
昨日までは夏日が続いていたというのに、今日はひどく寒い。
午後から降り出した静かな雨が、夜になっても新緑の若葉を濡らし続けていた。
俺の名前は岸達男、32歳。
いまだにふらふらと身を固めず、独身貴族を謳歌している。
今夜はやけに自分の中の衝動を抑え込めずに、ネオンの灯る飲み屋街へと出てきた。
一晩だけの都合の良い女はいないものかと、道行く人々に目を向けてみるが、土曜日の雨の夜だ。
多くはすでに雄雌の番いで、あいあい傘の下で仲睦まじくよろしくやっている姿を、公共の場に晒していた。
道端での誘いは諦めて、俺は一軒のバーに入ることにした。
幾度か訪れたことのある、こじんまりとした雰囲気の良いオーセンティックなバーだ。
「いらっしゃいませ。おひとり様ですか?カウンターへどうぞ。」
少しグレーの入った髪をオールバックにまとめたマスターが、6人掛けのカウンターの右端へ案内してくれる。
他の5席は埋まっていた。
「何になさいますか?」
「ウィスキーを。シングル、ロックで。」
俺のオーダーを受け入れ、こくりと頷くマスター。
酒が運ばれてくるまでの間、ポケットから取り出したマールボロに火を付け煙を燻らす。
灰白く染まる景色の向こう側に、良さそうな女性がいないかと店内を見回してみる。
静かなジャズが流れる店内。
店内は8割方埋まっていて、雑然とした会話の音が雨音のように耳に入ってくる。
そこに意味のある言葉があるようには思えない。
ただただ雨のように降り、形を成さずに流れ消えていく音だけがその場に溢れていた。
タバコの煙を、ため息とともに吐き出す。
その煙の中にはニコチンやタールの他に、微量にでも俺の魂的なものが含まれているのだろうか。
空中に吐き出された煙は、数瞬の内に消えてなくなっていく。
カウンターのマスターに目を向けると、丁寧にカットされた美しく丸い氷が入った厚みのあるグラスに、琥珀色の液体をメジャーカップから注いでいるところだった。
細く捻じられたバースプーンでグラスの中をゆるやかに混ぜると、氷の音が心地よく響いた。
「ウィスキー、ロックです。」
マスターの低い声が、やわらかく丸い形となって耳に届く。
3000ケルビン程の暖かな色をした店内の照明が、グラスの中でプリズムを作り出している。
生成り色の麻で作られたコースターの上に置かれたそれに、手を伸ばし口付けた。
焼けつくようなアルコールは臓腑を熱くさせ、芳醇なモルトと、熟成を感じさせるウッディーな薫りが複雑に口中と鼻孔を刺激する。
脳に心地よい痺れを感じ、昂っていた衝動が少し抑えられていく。
カランコロンとグラスの中の氷を遊ばせながら3口目を運ぼうとした頃、カウンターの中央4席の客がほぼ同時に立ち上がった。
札を数枚置いて、扉を開き順番に雨が降る夜の街に消えて行った男女2ペア。
俺はまるでスペードの5。ポーカーのあまり札の気分だ。
少し狭苦しいくらいだったカウンター席が伽藍となり、その空白に何の気なしに目をやれば、左端にひとり座っている女と目が合った。
ストライプの入った白シャツワンピース、腕にはセンスの良い革ベルトの小さな時計。
理知的な印象の顔立ちをした、同世代と思しき綺麗な女性だった。
目が合った気まずさをおくびにも出さず、お互いにこやかに会釈をする。
まるで、お互いに残り札になっちゃいましたね、と言わんばかりに。
彼女の前には飲み干されるのを待っているかのように、ショートグラスのカクテルがほんの少しだけ残っていた。
途中まで吸っていた2本目のタバコを灰皿に押し付ける。
ジジッと音を鳴らし消える火。
代わりに少しだけ心に火を灯してみる。
席を立ち、ゆっくりと歩を進める。
こちらを向いた女は顔で「なぁに?」と優しく問いかけてくる。
近くで見ると更にいい女だった。
ハートというよりはダイヤのエースといった雰囲気だった。
あまり札になるには、もったいない。
「こんばんは、美しいお嬢さん。良かったら、もう一杯、付き合ってくれませんか?」
「こんばんは、伊達男さん。良いですよ、よろこんでお付き合いしましょう。」
ありがとう、といって俺は女の隣の席に座った。
お互い空きかけのグラスをカチッと鳴らして乾杯し、簡単な自己紹介を交わした。
彼女の名前はチサトといった。年齢は俺の2つ下の30歳だった。
「今日は寒くなったね。」
そんな軽い雑談から入る。
「この季節の寒くなった日は、若葉寒って言うのよ。」
なんていう返事が返ってきた。
春の「花冷え」から季節が進むと、「若葉寒」なんていう言葉が充てられるそうだ。
ジャブへの返しとしては、なかなかキレのあるパンチが返ってきた。
が、悪くない。
聡明な女性との会話を楽しむこととしよう。
最後の一口を共に飲み干し、二人一緒に2杯目をオーダーすることにした。
「ギムレットなんてどう?」と俺は提案してみるが、
「うーん・・・モッキンバードなんてどうかしら?」とチサトが言い、
「モッキンバード?」と間抜けに俺が返す。
聞きなれないカクテルの名前だ。
彼女曰く、
テキーラにミントリキュールとライムジュースを合わせた、爽やかなカクテルらしい。
「じゃあ、俺も同じものを。」とマスターにオーダーした。
カクテルが出来るまでの間、俺は色々と質問してみた。
このバーには良く来るの?
仕事は何してるの?
趣味とかある?
時計ステキだね。どこのブランド?
初対面の俺からの質問に彼女はイヤな素振りも見せず、笑顔で楽しそうに答えてくれた。
会話の中で、二人ともに趣味が読書であるという共通点があった。
彼女は日本の古典文学などを扱う仕事に就いていて、日本の古い言葉や隠語などを調べるのがライフワークにもなっているという。
それで、「若葉寒」なんていう言葉も知っているのかと合点がいった。
彼女のときたま見せる、長い髪を耳に掛ける仕草がたまらなくセクシーだった。
耳に品よく添えられた、翡翠色の小さなピアスが小さく揺れていた。
10分ほどして、ショートカクテルが2つ置かれた。
新緑の季節にぴったりの、美しく透き通った緑色のモッキンバード。
零れないように乾杯して飲んでみる。
口に広がるのはテキーラのあの独特の香りと、ミントとライムの心地良い爽やかさ。
すっきりさっぱりとしたカクテルだった。
「うん、おいし。・・・モッキンバード・・・ものまね鳥か・・・。」
と、チサトは少し暗い目を緑色のカクテルに落として独り言ちた。
何か悲しいことがあったんだろうか。
どうかしたの?と聞く間も与えず、つとめて明るい調子で
「ねぇ、レイモンド・チャンドラーは読んだことある?」
と聞いてきた。
俺は頭の隅の方に、微かに引っ掛かっている記憶を引っ張ってきた。
「フィリップ・マーロウのシリーズ?」
「そうそう。私ね、中でもロング・グッドバイが好きで。」
「ハードボイルド物が好きなんだね。・・・あぁ、だからさっきギムレットはダメだったんだ?」
「あはは、『ギムレットには早すぎる』って?それは出来過ぎた話よ。」
そう言って、くすくすと笑うチサトはかわいい。
「でね、ロング・グッドバイの中で、マーロウとレノックスがバーで交わす会話があるじゃない?あそこのシーンとセリフが好きなの。」
「何だっけ?開いたばかりの静かなバーで飲む一杯目は最高だぜ、みたいなセリフだったっけ?」
「そう。静かなバーでの最初の静かな一杯―こんなすばらしいものはないっていうセリフ。その後にこう続くの。」
彼女はアルコールで薄桃色に染まった頬に、少し潤んだ目を俺から逸らして言葉を続けた。
「アルコールは恋に似ている。最初のキスは魔法のようだ。二度目で心を通わせる。そして三度目は決まりごとになる。あとはただ相手の服を脱がせるだけだ。」
「『どこがいけない?』」
「ふふふ、そう。どこがいけない?ってマーロウは返すの。」
いたずらっぽい目つきでチサトがこちらを見てくる。
目が合って数瞬、沈黙が流れる。
「・・・ねぇ、あなたは今夜何をしにここへ来たの?」
グゥっと心臓が掴まれた、ような気がした。
「私もあなたと同じ目的だって言ったら、どう思う?」
そう言って、チサトはカウンターの上に置いた俺の手に、自身の左手の指を這わせる。
「・・・どこがいけない?」
チサトの左手を取り、手の甲に軽く口づけをした。
彼女の顔は更に上気して赤みを増し、目はトロンとなり艶を帯びていた。
「ふふふ。じゃあ、ここを出て私の家へ行きましょ。すぐ近くなの。」
「君の家に・・・?」
「土曜の夜は、どこもいっぱいだよ。きっと。」
「あぁ、、、なるほど。」
「そんな警戒しなくても大丈夫よ。最近色々あったんだけど、今夜は気分が良いの。特別よ。」
「警戒なんてしてないさ。」
「ウソだー。ちょっと疑ってるでしょ?」
「君はキレイでステキな女の子だよ。」
「あはは、何その返し。笑っちゃう。あはは。」
チサトは大きく笑って、目尻に浮かんだ涙を拭った。
そしてこう言った。
「大丈夫よ。私、饂飩じゃないから。」
二人は立ち上がり、まだ雨のそぼ降る夜の街へと出て行った。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【饂飩】(うどん)
自宅に連れ込んで稼ぐ淫売婦という意味を持つ隠語である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後までお読みいただきありがとうございました!
この記事が気に入っていただけましたら下のボタンから共有お願いします!
-
前の記事

【3000文字チャレンジ】転生したら電鉄会社の社長になってた件 2020.05.19
-
次の記事

【3000文字チャレンジ】ぼくの愛機はCanon EOS 50Dです。 2020.06.06

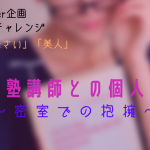
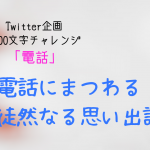
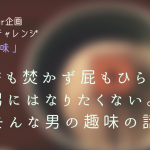

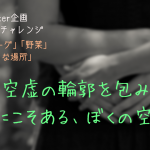
コメントを書く